|
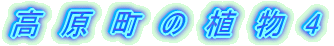
高原町にはどんな植物が生えているのだろう
2008年〜2011年
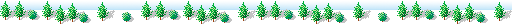
 
ジャゴケの雌器床(先端にぶら下がっている黒い部分) ジャゴケの雄器床(茶色の部分)
ジャゴケ:
いつもの散歩道で切通しの土手にコケがびっしりとついているので観察していましたが3年目にして今年初めて雌器床と雄器床が着きました。
花でいえば雄蕊、雌蕊というところでしょうか。こういうものが出てこないと私のような素人にはとても種の同定はできません。正確に種を同定するには顕微鏡が必要のようです。
歴史的には地上にまだ植物が進出していない時代にコケは最初に水中から地上に現れた植物だそうでうす。その一生は雄蕊と雌蕊があって花が咲き、実がなってそこから芽が出るというような単純なものではく、とても複雑です。
高原町(宮崎県)は愛知県などと比べると年間降雨量も多く、コケの成長に適した環境にあり、種類も多いのですが同定が困難な植物です。(2011.8.16)

シノブ:
高原町のほほえみ館前の駐車場のクスの木を見上げていたら、シダが目につきました。小指ほどもある根から葉が出ていました。
図鑑には深い山の岩や樹幹に着生すると書かれていますが、ほほえみ館は深い山ではないものの木にはコケもはえ、この辺りは湿度も高いので元気なのでしょう。(2011.7.15)

ツルアジサイ:
梅雨時のこの時期になるとアジサイの花がきれいです。このツルアジサイは見栄えのするアジサイではありせんが、楚々として可憐な風情が何とも言えません。
いつも通る道の横の杉の木に絡みついたツタから突然花が咲き、初めて気づきました。(2011.6.15)

エイザンスミレ:
皇子地区の半日日陰の道の土手に比較的まとまって咲いていました。3年位前から気づいていましたが、花期が短く、なかなか咲いている時に出会えませんでした。
スミレとは思えないような葉が特徴です。よく似た種類にヒゴスミレがありますが、葉がもっと細くなるのが特徴のようです。(2011.5.15)

オオアラセイトウ:
別名、ショカツサイ、またはムラサキハナナ、またはハナダイコンなどと呼ばれます。中国原産の越年草と図鑑には記載されています。
未だ霜が降る2月の下旬に杉林の下の土手に咲いていました。元々は栽培種でしょうが、今では空き地などに春に先駆けて咲くようです。
昔はショカツサイと呼ばれた時期もありましたが、アブラナ科オオアラセイトウ属のため、オオアラセイトウの名前が定着したようです。(2011.3.15)

ヤブコウジ:
城の下は戦国時代に高原城があった辺りの東側や北側を指す地名らしいのですが、その迫を歩いていて見つけました。道の横の崖に生えていました。実は赤くつやつやして目立つのですが丈は20センチほど、実も2,3個と少なくて余りぱっとしません。センリョウ、マンリョウに対してイチリョウと言われる所以です。
(2011.2.15)
 
エンコウカエデ:
12月の中旬に御池の周りを散歩していたら高さ1メートルほどの紅葉した木を見つけました。12月の中旬に未だ紅葉した木があることに驚きました。それと御池の周りにはそんなに紅葉する木が多くはないので特に目立ちました。
家に帰って図鑑で調べてみたら葉の形からエンコウカエデのようでした。エンコウは猿猴と書きます。つまり猿のことです。図鑑にはこの形がテナガザルの手に似ていることから命名されたと記載されていました。(2011.1.15)

ホシダ:
3年ほど前に小林市の木浦木に行った時に面白発見塾の松本さんからこのホシダを教えていただきました。山奥にあるシダと思っていましたが、最近散歩の途中の崖などに普通に見られ、驚くほど普通のシダです。図鑑にも…山野、路傍など人為的な環境に普通に見られる雑草的なシダで、暖地に多い…と記載されています。(2010.12.20)

ハチジョウカグマ:
葉の表面に無性芽が着いています。この無性芽はコモチシダに着くのではよく知られていますが、これはハチジョウカグマに着いた無性芽です。最初はこのシダはコモチシダかと思いましたが、よく調べたらハチジョウカグマでした。毎日の散歩の途中の崖の上にありました。それ以来気をつけてみていると御池にも多く見かけました。
(2010.11.15)

ジュズダマ:
水路の土手に1本だけジュズダマが一杯実をつけていました。周りの草が刈られているのに背の高いこのジュズダマだけが残っています。この向こうの田んぼの地主さんが、土手の草を刈る時にわざわざこのジュズダマだけを残したのでしょう。向こうの田んぼの稲同様に豊作です。
昔はこの実に糸を通して数珠にしたり、お手玉の中に入れたりしていろいろ使われましたが、今はそのようなことをする人もいないのではないでしょうか。(2010.10.15)

気根:
初夏の頃、御池を散策していたら見上げるような高さから 1m以上の気根がぶら下がっていました。毎年短い気根は見ることができますが、このように長い気根を見たのは初めてです。今年の夏は異常に雨が多いのでこのような現象が起きたのでしょうか。
この木の名前がよくわかりませんでしたが、ツル植物で、カギカズラ?ではないかと思っています。(2010.9.15)

ヤグレガサの群落:
昨年、大幡山の登山口付近でヤブレガサの群落を見つけたので写真を撮ろうと思い、出かけましたが、道が壊れていて行けませんでした。ところが車で帰る途中にこの群落を発見しました。高千穂の峰、矢岳に行く人は必ず車で通るところなのにびっくりです。
もっと新芽の頃には山菜として食べることができるそうですが、私は食べたことがありません。
(2010.7.15)

マイズルテンナンショウ:
昨年も通っていて気づきませんでしたが、いつもの散歩道の横の土手にひっそりと咲いていました。
マムシ草の仲間ですが、茎にマムシ模様がなく肉穂上部の付属体は筒内から高くでて直立していて品があります。
マイズルテンナンショウは舞鶴天南星で、小葉が鶴が翅を広げた形に見立てた命名だそうです。
サトイモ科テンナンショウ属(2010.6.16)

ウラジロ:
2月の末に御池の周りを歩いていたら道の端にウラジロがあり、春にさきがけて既に新芽が出始めていました。私が昔住んでいた愛知県では正月の鏡餅の下にこのウラジロを敷くのが慣わしでした。ウラジロはこの写真のように二股に分かれた中心から新芽がでて、その先がまた二股に分かれてゆき、下の葉も枯れず代を重ねてゆくことからめでたいということで鏡餅の下に敷くと聞いたことがあります。(2010.3.15)
:

ヒトツバ:
この写真は御池の周りある倒木に生えていたものです。
この辺りではよく見かけるシダです。図鑑にも「…関東地方以西から琉球で、やや乾燥した岩上や樹幹に着生し、暖地に行くほど普通に見られる…」と記載されています。
この写真のように裏は灰褐色ですが、時には赤と見間違うほどの色をしているものもあります。(2010.2.15)

ヤブツバキ:
12月の下旬に御池で撮った写真です。霜のせいか、花びらの一部が霜枯れしています。ヤブツバキの学名はカメリア・ジャポニカで、日本の椿の原種と言っていいのではないでしょうか。図鑑によれば2、3月ころに花が咲くと書いてありますが、この辺りでは年末から既に咲き始めるようです。ヤブツバキばかりではなく、我家のワビスケも咲きだしました。(2010.1.15)

シシガシラ:
この写真はサンヨーフラワー温泉付近で見かけたものです。家の近辺では余り見ません。図鑑には記載されていませんが、小林生物愛好会の松本さんの話では比較的標高の高い所に生えるとのことでした。葉の裏に胞子が付かず、ゼンマイと同じように胞子葉が春に葉の根元の中心に立ち上がってきます。
(2009.12.15)
 
タマシダ:
高原町の清流ランドを散策していたら崖のようなところに生えていました。シダ類は花が咲かない上に似たような葉でとても同定が困難であるとは、シダ類図鑑にも書かれていることです。しかし、このシダは一度見たら忘れられない葉の形をしています。
この形から生け花にも用いられ、よく家庭で栽培しているのを見かけます。(2009.11.15)
 
イノデ 鹿に食われたイノデ
イノデ:
図鑑によればイノデとは「猪の手」という意味だそうです。根元から茶色の毛に覆われています。
それが猪の手のようだ、ということで命名されたということです。毛のようなものは鱗片だそうです。
雑木林の下辺りに多くは生えています。鹿はシダを余り食べませんが、このイノデの葉だけは余程好きらしく、葉が見事に食べられていました。右の写真は皇子地区の雑木林の下で沢山見かけたものです。(2009.10.12)

ツルボ:
8月中旬、道端に咲いていました。今年は天候不順で雨が多く、気温は低めのせいか、花の咲きだしがいつもと違うようです。図鑑には初秋の頃と記載されています。私の記憶でも9月に咲く花と思っていましたので意外でした。(2009.9.15)

オオバノイノモトソウ:
この写真は御池の周りで5月ころに写したものです。右のものと左のものと一見異なる種類のように見えますが、実は同じオオバノイノモトソウです。左の葉の細い方はこの春に芽が出たものです。秋にかけて右のような葉になるようです。
都城植物愛好会副会長の松本さんによれば隣町の小林市では約200種類のシダ植物が確認されているそうです。当然のことながらこの高原町でも200種類前後のシダ植物があると推測されます。これから少しシダ植物を調べてみようと思います。(2009.8.15)

ホソバシロスミレ:
いつもの散歩道で見つけました。去年もここを通って散歩していたのに気がつきませんでした。コンクリートの塀と側溝の間のあるか無きかの隙間に根を張り花を咲かせています。その生命力に感嘆するばかりです。
図鑑によればシロスミレの変種として中国、四国、九州の山地に生える、とあります。
シロスミレ自体は本州中部以北の山地と北海道に生えるそうです。(2009.7.15)

タツナミソウとコバノタツナミ:
前々からタツナミソウとコバノタツナミとの違いが判らず困っていました。今回、それぞれ違う場所に生えていて、明らかに違いがあるタツナミソウが目についてので比べてみました。花の着き方、花の色、そして最も違うのは葉の蝕感です。左のコバノタツナミの方が葉が柔らかく、ビロードのような蝕感があります。(2009.6.15)

シロバナタンポポ:
中学時代、生物の時間で、愛知県では昔は生えていなかった、他所の土地から来たものである。種が貨車などで運ばれて来たので線路の近くに多い、と教えらました。
この西諸地方の老人には昔はタンポポは白しかなかった、と言われました。そうしてみるとシロバナタンポポは九州の在来種で、愛知県地方まで広がったのではないでしょうか。(2009.3.15)

ヒメノキシノブ:
矢岳に登る途中の木に生えていたヒメノキシノブです。写真の如く葉の先が尖らずに丸い感じです。図鑑にも「北海道西部以南の山地の樹幹や岩上に着生」と書いてありました。
ノキシノブなんて1種類しかないと思っていましたが、その他にもミヤマノキシノブやツクシノキシノブなどがあることを最近知りました。(2008.10.15)
 フジバカマ: フジバカマ:
霞ケ丘の急斜面に野生のフジバカマが咲いていました。最近は野生のものは余り見かけません。しかし、原産国は中国で、奈良時代に日本に入ってきたようです。長い間に野生化したものです。最近はよく庭に植えられています。
図鑑には「この草を乾かすとクマリンの香りを出すので、昔中国では浴湯にいれ、…」とありましたたので、我家でも庭のフジバカマで試したたことがありましたが、余り香らなかったように思います。
(2008.10.15)

サイヨウシャジン:
こちらに来てずっとこの花をツリガネニンジンと思っていましたが、確認のために図鑑に当たりましたら、ツリガネニンジンはサイヨウシャジンの変種であり、主に本州に生えると、書いてありました。
サイヨウシャジンは主に四国、九州に生え、花冠の先がわずかにくびれてつぼ型になり、花柱が長く突き出すと図鑑にあります。サイヨウとは細葉のことですが、必ずしも葉は狭くなく、狭いものから広いものまであるそうです。(2008.9.15)

トチバニンジン:
いつも散歩に行く途中の雑木林の林縁に生えていました。毎日通っていても全然気が付きませんでしたが7月の中旬に赤い実をつけ、その存在を誇示しました。
図鑑には「朝鮮人参と地上部ではほとんど区別できないほど似ているが、トチバニンジンは地下茎が太いのに対して、朝鮮人参は根が太い」と書いてあります。
朝鮮人参とそっくりということで、民間では朝鮮人参の代用として用いられているようですが、図鑑には薬効が有るとは書いて有りませんでした。(2008.8.15)
 
クマノミズキ:
普段散歩している時はそこにこの木があるのに気付かないのに6月下旬に白い花を一杯付けます。山などに生えているときは他の木との競争で下の方に枝が無く、花は上のほうに咲いていますが、この木は道路際にあるために花も比較的下の方にあり、アップで写真を撮ることが出来ました。(2008.7.15)

ツルコウゾ:
6月初旬、梅雨の晴れ間に散歩に出かけて見つけました。道の土手にクマイチゴやナガバモミジイチゴが生えていて、時々つまみながら散歩をする場所です。
このイチゴの実と後の緑の濃い葉が目に留まりました。この写真では判りにくいのですが、この濃い緑の葉はウルシの葉です。ウルシにイチゴの実がなっている、と瞬間的に思ってしまいました。良く見ればウルシの木にこのツルコウゾが絡み付いているのです。この実は美味しかったですが、後で唇が腫れてこないか少し心配でした。(2008.6.15)

ジャケツイバラ:
新しく出来た道路の横の杉林が切り払われた後にススキやワラビなどが生えてきており、その間に目を見張るような黄色い花が咲いていました。
最初に見たとき、ニセアカシアのような丸い葉と鋭い棘、そしてケバケバしいほど目立つ花から、これは外来種の花と思いましたが、図鑑で調べたら、日本の在来種のようです。
図鑑によればジャケツイバラは蛇結茨と書き、茨のからむ様子が、蛇がとぐろを巻いた形に似ているところからついたと言われている、と書いてありました。
(2008.5.15)

キケマン:
ムラサキケマンはこの辺りでは田んぼの畦草といっていいほど珍しくありませんが、キケマンは今まで見たことがありませんでした。3月末に皇子原公園の横の土手に少しだけですが咲いていました。
キケマンとは黄華鬘と書きます。花の形が黄色のケマンという意味だそうです。では華鬘とは何だろう。ケマンとはお寺の本堂にかけてあるものであるというのを昔本で読みました。この春あれがケマンであると、あるお寺で教えられました。だがケマンの形とこの花の形が似ているとはとても思えませんでした。。(2008.4.15)

コショウノキ:
まだ何の花も咲いていない早春の山の麓を歩いていると一瞬白いジンチョウゲ咲いていると錯覚します。ジンチョウゲはもともと園芸種なので不思議な気がします。それもそうで、ジンチョウゲと同じジンチョウゲ科の植物です。
コショウノキとは不思議な名前ですが、勿論、この木から胡椒が取れるわけではありません。7月頃に赤い実がなり、その実が辛いことからの命名のようです。(2008.3.15)

マンリョウ:
これは我家の庭のツバキの根元に生えてきたマンリョウです。写真では判りにくいですが、右側には白いマンリョウ、左側には赤いマンリョウです。これは私たちが種を蒔いたのではなく、どうも小鳥たちが種を蒔いていったようです。マンリョウは移し変えると枯れる傾向があるのでそのままにしてあります。(2008.2.15)

キカラスウリ:
12月末に散歩道の途中になっていました。この辺りでは普通のカラスウリは目立ちますが、キカラスウリは余り目立ちません。(2008.1.15)
身近なよく知っている植物から名前を調べましたが、知らない植物ばかりです。今後どのくらい植物名を増やすことが出来るか?。
|


















 フジバカマ:
フジバカマ:








