|

主に陸産貝類を中心に探してみようと思います。
貝の同定はほとんど出来ません。その多くを元宮崎南高校教頭の西俊夫先生に教えていただきました。
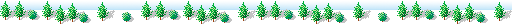

リンゴクスミガイの卵塊(リンゴガイ科)
散歩に行く途中にある田んぼの岸一面におびただしいリンゴクスミガイの卵塊を見つけました。
卵塊 1個に200から300個の卵があるそうで、数えたわけではないですが、この田んぼでは数万から数十万匹のリンゴクスミガイが生まれそうです。
このまま田植えをしても大丈夫なのか心配です。(2022、7、15)

タカチホマイマ交接(ナンバンマイマイ科)
朝、庭の草取りをしていたらアマドコロの葉の裏でタカチホマイマイが交接していました。
カタツムリは雌雄同体です。ですからお互いの精子を交換して卵を産みます。いわゆるツノの下に生殖門があり、そこからお互いの精子を交換するのです。この写真は精子を交換している様子です。(2021、9、15)

ナミギセル(キセルガイ科)
庭の隅の物置小屋の後の草を引いていたら落ちていました。我が家にこんな大きな(体長2.4ミリ)キセルガイは始めてでした。
アメイロギセルではないかと思いましたが、一応貝類の専門家の西先生に同定していただきました。ナミギセルとの事で、図鑑で調べて見たら、「市街地や山地の…」書いてありました。(2021、5、15)

アラナミギセル(キセルガイ科)
4月に清流ランドに行ったときに見つけました。しかし、図鑑で調べてもどうしてもわからず、貝の専門家の西先生にお聞きしました。
貝類の同定はなかなか難しいです。(2020、5,15)

コベソマイマイ:(ナンバンマイマイ科)
我が家のすぐ近く、わが家から20メートルほどの道路上に落ちていました。普通コベソマイマイは「市街地周辺の森から産地までの林内の落ち葉の下に生息している。と図鑑に記載されています。しかし、落ちていた近くには森もありません。どうしてこの路上に落ちていたのか分かりません。我が家の近所に住んでいるのか今後見てゆきたいと思います。(2018、11、15)

ヤマクルマガイ:(ヤマタニシ科)
柿の木の下にあるミョウガの根元にこのヤマクルマガイが落ちていました。
私の家の土地は20年前に家を建てるときに客土をして土盛りをしましたので、最初はカタツムリの類がいませんでしたが、最初にウスカワマイマイが、その後にタカチホマイマイが、そして近年オカチョウジガイががやってきました。今年このヤマクルマガイが我が家にやってきました。(2018、8、15)

イロアセオトメマイマイ:(オナジマイマイ科)
皇子原を歩いていたら、葉っぱの上に小さなカタツムリを見つけました。殻の直径が3mmほどでした。
一応確認の為に西先生に同定のお願いをしました。
イロアセオトメマイマイは漢字で書けば「色褪せ乙女マイマイ」となりましょうか?名前の由来を調べてみましたがよくわかりませんでした。(2018、6、15)

ウスカワマイマイ:(オナジマイマイ科)
我が家の前の道路を挟んで耕作放棄地があります。時々ミミズが出てきて耕作放棄地に帰れず死に、死体がたくさん転がっています。そこに雨が降ると乾燥したミミズがふやけるのでしょうか、耕作放棄地からウスマワマイマイが出てきてこのミミズの死骸を食べていました。その数20匹ほどもいました。
もう20年ほども前に買ったカタツムリの本には腐肉を食べるのはタワラガイなど特殊な貝類と書いてありましたので驚きました。(2017、6、15)

クスミリンゴガイの卵塊:
御池から流れ出た水が水路を通ってここ後川内の田んぼにまで流れて来ているようです。数年前に来た時もここの田にクスミリンゴガイの卵塊が稲についているのを見ました。今年、この田も休耕田になったようです。まばらに生えた雑草にクスミリンゴガイの卵塊が一杯ついていました。(2015、10、15)

ヤマタニシ:
雨上がりに散歩していたらこのヤマタニシが歩いていました。固い殻を背負っているだけあって、肉の部分が肉厚で力強さを感じるカタツムリです。(2015、9,15)
 
オオタニシ:
12月の出の山のホタル幼虫調査の帰りに、西先生が御池にオオタニシがいるとの情報が入ったので、御池に探しに行くと言われるので、同行しました。なかなか見つけることが出来ませんでしたが、私が採集しました。左の写真は西先生から頂いものです。
西先生からは「過去のデータを調べたところ昭和10年に黒田徳米氏が小林と高鍋で確認しています。その後25年くらい前に私の息子が宮崎市で確認しました。今回は宮崎県で4カ所目の産地となりそうです。
オオタニシは環境省のRDBでは準絶滅危惧種(NT)になっています。」との報告を頂きました。(2015、1、15)

コベソマイマイ:
皇子原を歩いていたら、倒木の横に大きなコベソマイマイが2匹歩いていました。一目見てコベソマイマイと判りました。高原町にはコベソマイマイはよく見かけるカタツムリと言っていいと思います。(2014、10、15)

ギュリキギセル:
御池キャンプ場に大きなケヤキの木があり、下の方が空洞になっていてそこに沢山のアズキガイに交じってこのギュリキギセルがいました。
同定していただいた西先生によると名前のギュリキは命名者の名前とのことです。(2014. 9.15)

オカチョウジガイ(オカクチキレガイ科)
ホソオカチョウジガイ(オカクチキレガイ科)
ヤマクルマガイ(ヤマタニシ科)
上がオカチョウジガイ。下の左がホソオカチョウジガイ。右側がヤマクルマガイです。ホソオカチョウジガイの長さは5mmほどしかありません。
知人からカブトムシの幼虫を頂きました。その時、カブトムシの住んでいた畑の土も頂きました。数日してみたら土の表面にこの貝達がいました。このオカチョウジガイはヒメボタルの餌として有名です。(2014、7、15)

ヤマクルマガイ:
12月の初旬に窓ガラスを掃除していたら、家の犬走りにこのヤマクルマガイが転がっていました。陸産貝類図鑑によれば「…タブノキ、ヤブニッケイ、ウバメガシなどの樹間の落葉下に棲息する…」とありました。我家は野中の一軒家ではありません。いわゆる分譲地で大きな木もありません。どうやってこの森に棲むヤマクルマガイが我家にやって来たのかわかりません。(2013.12.15)

マルタニシ:
タニシは昔から探していましたが、なかなか見つけることができませんでした。お盆過ぎにに孫が遊びに来て、孫と散歩に行ったら、いつもの散歩道で田んぼの中のこのタニシを孫が見つけました。
子供時代に自分の家の田んぼには」タニシが一杯おり、稲刈りの後に集めて食べたことを思い出しました。けっこう美味しかった記憶です。(2013.9.15)

モノアラガイ:
5月下旬に御池の周りを散歩して水際の石をひっくり返してみたら、石の下にいました。
昔住んでいた愛知県ではヒメモノアラガイがほとんどでモノアラガイを見たことがありませんでした。
愛知県ではサカマキガイやヒメモノアラガイが田んぼの脇の水路に大量に発生してヘイケボタルの幼虫の餌になっていました。
(2011.6.15)

ナミコギセル:
愛知県にいたころこのナミコギセルは家の裏の畑に沢山いて、珍しいことはありませんでした。
しかし、高原町に来てこの貝をなかなか見つけることができずにきました。意外にもご近所のブロック塀の上にいました。今、私の住んでいる所は新興住宅地なので居ないのかもしれません。古くからある家の庭には珍しくないのかもしれません。
(2010.10.15)

ノナメクジ:
毎朝の散歩道で、道の片側は田んぼ、片側は水路というところです。水路の横にはやはり田んぼです。
現時点においては宮崎県では比較的珍しい種類のようです。(2010.8.15)

コベソマイマイ:
右側の小さい貝は私が御池で拾ったものです。貝の種名がわからず西先生にお見せしたところ、左の大きな貝をいただきました。こうして並べてみるとなるほどコベソマイマイだとわかります。(2010.6.16)

シリオレギセル:
2007年の春に長尾山で貝殻を拾ったことがあり、このHPの下の方に掲載されています。このシリオレギセルは御池をはさんだ反対側の祓川神社からの登山道で見つけたものです。
図鑑によれば、幼体と成体とでは色も巻き数もことなるようです。(2010.1.15)

イロアセオトメマイマイ:
小林生物愛好会の定例会が御池で行われ、御池の遊歩道の木の葉の裏にいました。
殻が半ば透き通りとても模様がとてもきれいなカタツムリです。
殻径約 8mmで、同行した西先生によれば「未だ子供です」とのことでした。図鑑によれば成貝は殻径は約14mmと記載されていました。
更にイロアセオトメマイマイは九州南部と甑島に産すとのことでした。ある面で珍しいカタツムリでもあります。(2009.10.15)

カタギセル:
このカタギセルも霧島東神社の裏から高千穂の峰に至る登山道で見つけたものです。
キセルガイの仲間はどれも同じに見えてしまいますが、西先生にお見せしたらたちどころに種名が出てきます。どこで見分けるのか聞きましたところ、貝の口の所の違いだそうです。(2009.8.15)

アメイロギセル:
霧島東神社の裏から高千穂の峰に登る登山道があります。神社の裏から10分ほども登った所の倒木の下にぶら下がっていました。西先生にアメイロギセルである、と同定して頂きましたが、家に帰って陸産貝類図鑑で調べましたが、図鑑には記載されていませんでした。後日、先生に聞きましたら、昔はクロギセルと言っていたかもしれない、とのことでした。
図鑑には九州西部に分布と記載されていました。
それにしてもこのアメイロギセルは老化しているのか、アメイロとは程遠い色をしていて、どちらかと言えばクロギセルという名前の方が似合うような気がします。(2009.6.15)

カタツムリの異常発生:
6月下旬の梅雨真っ盛りの晴れ間に散歩に出ました。昨夜の大雨を避けて田んぼの土手のチガヤにウスカワマイマイが登っていました。しかし、異常としか言いようが無いほどの数でした。(2008.7.15)

カタギセル:
4月27日に小林生物愛好会の観察会が皇子原公園でありました。ここは公園とはいえ、植栽された木はほとんどなく、ほぼ自然の状態です。雑木の根元には朽木が落ちており、西先生が朽木をひっくりかえした中にこのキセルガイがいました。西先生は直ぐに「カタギセル」とこの貝の名前を同定しました。
頂いて家に帰り、日本陸産貝類図鑑をみても、説明の文章を読んでもこの貝がどうしてカタギセルと判るのかまったく判りません。(2008.5.15)

タニシ:
昨年11月に小林市の千谷湧水の下部に行きました。そこは千谷湧水から流れ込んだ水が休耕田の間に細い水路となっている所があり、そこにタニシばかりでなくカワニナやヌマエビなどがいました。その場所は小林市と高原町との境目にあります。
1月の初旬にタニシの写真を撮ろうと思い出かけました。しかしながら茂っていた草はなく生き物の影は何もありませんでした。かろうじてこのタニシの殻を見つけました。近年、農薬の使用でタニシも今では絶滅危惧種に近いのでは無いでしょうか。滅多にお目にかかれません(2008.1.15)

シリオレギセル:
御池の東側に連なり、都城市に連なる長尾山は自然が一杯残っています。稜線上の道が高原町と都城市を分けています。
ここで拾ったのがこのキセル貝です。生きた貝を探しましたが見つける事が出来ませんでした。(2007.5.15)

ヤマナメクジ:
2月の下旬、3月末の気温といわれた朝に、我家の玄関前の通路を歩いていました。7センチほどのナメクジです。西先生によれば大きい物は20センチ近くにもなるそうです。(2007.3.15)

ヒメモノアラガイ:
モノアラガイ科の貝。大きくても1センチあるかないか位の大きさです。ヘイケボタルを発見した辺りを探したら、ヘイケボタルの幼虫の餌であると言われているヒメモノアラガイを見つけました。愛知県の私の住んでいた町は主にサカマキガイがその餌でした。現在のところ、ここ高原町ではサカマキガイは見られません。(2006.7.15)

ナメクジ:
4月に入って流石に暖かくなってきましたので庭の草を引いていたらミカンの木の下の霜よけの藁の下から2匹のナメクジが出てきました。水をかけてやったら元気に動き出しました。ナメクジも貝の仲間です。(2006.4.15)

ドブガイ:
広原の温谷にある養魚池の下の水路に13センチほどもあるドブガイの大きな殻が落ちていました。(写真左)そのあたりの砂を掘ってみたら右の生きたドブガイが出てきました。最初、この貝をカラスガイと思い、2006年2月15日にはカラスガイとしてこのHPに紹介しましたが、今日2月19日に西先生にお会いしたら、九州にはカラスガイはいないと言われ、ドブガイであるとの指摘を受けましたので訂正します。(2006.2.19)

ダコスタマイマイ:
近くの雑木林の林縁で見つけました。殻径約12ミリほどの小さなかたつむりです。図鑑によれば九州南部・大分県東部に分布する、と記載されています。

ヒメオカモノアラガイ:
我家の庭にはこのヒメオカモノアラガイ、コベソマイマイ、ウスカワマイマイ、キリシママイマイがいます。その中で最も小さいカタツムリがこのヒメオカモノアラガイです。普段はほとんど気付かないのですが、雨が降ると門から玄関までのコンクリートの短い通路にやってきます。

コベソマイマイ:
キリシママイマイと共にこの辺りで人家の庭で普通に見られるカタツムリの内で最も大きい種類です。
 
クスミリンゴガイ:(ジャンボタニシ)
6月1日に御池で岸近くの岩に気持ちの悪いピンク色の卵魁を見つけました。その近くを探したら親貝がいました。
その大きさに驚くばかりです。写真撮影の為、持ち帰り、水の無い水槽に入れておいたら翌朝には水槽の壁に卵魁がひとつ産み付けられており、卵の数は約110個でした。その生命力には恐れ入るばかりです。
今問題の南米からの外来種です。こんな山奥の池にまで誰かが持ち込んだのでしょう。

マシジミ:
田んぼの間の水路にいました。殻もあり、ひょとしたらゲンジボタルの幼虫の食い跡かも。ここでゲンジボタルが発生しているかもしれません。

アズキガイ:
昨年の夏、カブトムシのいる木にいました。樹液を食べるのでしょうか。人の目の高さにいました。濡れるときれいな小豆色になることからアズキガイというそうです。

コモチカワツボ:
この辺りは湧水が多いのでその水を利用して鯉や鱒などの養魚が盛んです。この貝は日本の在来種ではなく、ニュージーランドから輸入された養魚用の魚の卵の容器に付着して来たらしいと言われています。
高原町でカワニナもいないのに養魚池の下流で蛍が異常発生したことがあり、調査したことにより発見されたそうです。4ミリほどと小さいので蛍の一齢幼虫の生存率を上げるのに役立っているようです。

カワニナ:
勿論、陸産貝類ではありません。ゲンジボタルの幼虫の餌として有名です。祓川の湧水のすぐ下の流れの中にいます。昨年6月ここにゲンジボタルを見に来ました。あまり多くはありませんでしたがゲンジボタルの優美な光を堪能しました。

ヤマクルマガイ:
愛知県の私の住んでいた辺りには棲息していなかったカタツムリです。図鑑によれば本州中部以南、以西と四国九州に棲息となっていまいした。臍孔は写真の如く深い。三角錐のフタがあるカタツムリです。移動の時はこのフタを頭に載せた格好で歩きます。
全体的には平たいカタツムリです。

黒いカタツムリ:
黒いカタツムリ、ん、新種?、と思いましたが、ウスカワマイマイの黒いものでした。食べ物の影響で黒いものが出来るようです。

ヤマタニシ:
恥ずかしながらフタのあるカタツムリを見たのは初めてでした。林の中の腐葉土の中にいました。この辺りでは結構いますし、貝殻も多いです。

ウスカワマイマイの交尾:
カタツムリは雌雄同体ですのでお互いの精子を交換します。カタツムリの右側の首の触角と殻口の中間くらいのところにある生殖門という穴にお互いの陰茎を差し込んで精子を交換します。ウスカワマイマイは愛知県の自宅にも多かったですが、数の上ではこちらの方がはるかに多いです。

キリシママイマイ:
このあたりに普通のカタツムリです。西先生によれば、霧島山(高千穂の峰を中心とした連山を指す)の近辺にいるものをキリシママイマイとよび、それ以外で棲息するものをタカチホマイマイというそうです。
殻の横線には変異あり、同定を困難にしています。
2
| № |
種名 |
科名 |
| 1 |
アズキガイ |
あずきがい科 |
| 2 |
ドブガイ |
いしがい科 |
| 3 |
コモチカワツボ |
いつまでがい科 |
| 4 |
ヒメオカモノアラガイ |
おかものあらがい科 |
| 5 |
イロアセオトメマイマイ |
おなじまいまい科 |
| 6 |
オナジマイマイ |
おなじまいまい科 |
| 7 |
タカチホマイマイ |
おなじまいまい科 |
| 8 |
ウスカワマイマイ |
おなじまいまい科 |
| 9 |
ダコスタマイマイ |
おなじまいまい科 |
| 10 |
アメイロギセル |
きせるがい科 |
| 11 |
カタギセル |
きせるがい科 |
| 12 |
シリオレギセル |
きせるがい科 |
| 13 |
ナミコギセル |
きせるがい科 |
| 14 |
ナミハダギセル |
きせるがい科 |
| 15 |
ノナメクジ |
こうらいなめくじ科 |
| 16 |
マシジミ |
しじみがい科 |
| 17 |
クスミリンゴガイ |
たにし科 |
| 18 |
タニシ |
たにし科 |
| 19 |
ナメクジ |
なめくじ科 |
| 20 |
ヤマナメクジ |
なめくじ科 |
| 21 |
カワニナ |
なわにな科 |
| 22 |
コベソマイマイ |
なんばんまいまい科 |
| 23 |
マルシタラガイ |
べっこうまいまい科 |
| 24 |
ヤマタニシ |
やまたにし科 |
| 25 |
ヤマクルマガイ |
やまたにし科 |
2013年11月15日更新
初回:5種類
|









































