|
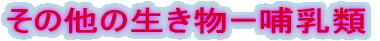
| 愛知県から引っ越してきてもっとも嬉しかったことは大型哺乳動物に遭遇することです。 比較的身近に遭遇しますが、写真を撮るのは極めて困難です。 |
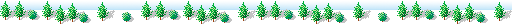

タヌキ(イヌ科)
交通事故に有ったようです。散歩の途中で見かけました。我が家から100メートル位しか離れていません。この場所の両側は家が立ち並んでいます。
太って大きなタヌキでした。(2023、11、15)

コウベモグラ(モグラ目、モグラ科)
13日の朝家の玄関まえに死んでいました。体長13センチ程ですこし小さいモグラです。死因は分かりません。我が家の庭は四方をブロックで囲んでいますので、よその土地からきたものでは無いでしょう。
(2023、10、15)

イタチ(イタチ科)
11月の末の暖かい日に庭にイタチがやって来シャクナゲの根元を掘ったりして、盛んにエサを求めているようでした。
窓越しに写真を撮ってみました。
前々からイタチの見せ糞が庭の通路にあり、時々イタチが我が家にやってくるのは知っていましたが、昼間姿を見るのは初めてでした。
イタチは昼間も行動することは知っていましたが、動きが早いので写真を撮ることはとても難しいです。
(2021、12、15)

クマネズミ(齧歯目 ネズミ科)
朝起きて、我が家の門扉から玄関の間にネズミの死骸が落ちていました。カラスかなんかが落としていったようです。
全身がないのではこのネズミの名前は同定できないと、思いましたが、一応図鑑で調べてみました。意外にもこの大きな耳が決め手でクマネズミと分りました。
(2021、11、15)
 
コウベモグラ(モグラ目 モグラ科)
6月初旬に散の途で見かけました。
この辺りはどこの家でも広い庭や家庭菜園があり、モグラがいても不思議ではありません。門から出たのはいいですが、今度は他所の家にはブロック塀があり、他所の家の庭には入ることが出来なかったようです。(2021、6、15)
 (ネコ目イタチ科) (ネコ目イタチ科)
午後の散歩、16:00頃田んぼのふちにアナグマを見かけました。昼日なかにアナグマに遭遇することはわりにあることですが、こんな身近な所で見かけるのは初めてです。
アナグマも私を見て警戒して動かなかったので良い写真が撮れました。(2021、4、15)

ムササビのエビフライ
2月に御池に行ったら、池に降りる木の階段にこの松ぼっくりの食べ残しが落ちていました。これはムササビが松の実を食べて食べ残しを捨てたものです。
宮崎県にはリスがいませんが、本州の方ではリスのエビフライと言われています。
前にもこのHPに記載しましたが、最近見かけませんでしたが、未だ元気にこのキャンプ村に住んでいることが分かり安心しました。(2021、3、15)

テン(イタチ科)
我が家から1キロくらいの所で、いつも買い物にゆく道でテンが交通事故にあっていて道の真ん中に転がっていたが、余り人の通らない所で、次の日ににもそのままになっていたので、道の端に片付けました。
ところがそれから3日後に又テンの死骸が路上に、同じ所で又交通事故にあったようで、道の傍に片付けようとしたら、腸が食べられて無くなっていました。
どうやら道の傍に片付けたテンの死骸をカラスが食べる時に道の傍から引っ張り出したようです。
この時期はタヌキやテンなどの交通事故をよく見かけます。子供が独り立ちして慣れない車と衝突するようです。(2019、11、15)

アナグマの仕事
8月10日に草引きに庭に出たら、アスパラガスの根元に深さ30センチ、直径30センチの穴が開いていました。私たちが寝ている間に庭に入り込んで穴を掘ったようです。
2014年にも穴を掘られたことがありました。
アナグマも一年中庭に来るのではなく、ある一定の時期にやってくるようです。アナグマが来るようになると、いつも庭にやってくるノラ猫が来なくなります。(2019、8、15)

イタチの糞:
我が家の玄関から門に至る通路の真ん中にかわいい糞がしてありました。イタチの糞です。イタチは夜行性ですのであまり姿を見ませんが、見た時も大層素早いので写真がありません。
余談ながらイタチとテンは同じイタチ科に属しています。胴が長いところが似ていますが、テンの方がはるかに大きいので直ぐに分かります。先日我が家の庭をテンが昼日なか横切るのを見て大いに驚きました。(2018、12、15)

ムササビ:(リス科)
昨年4月にブッポウソウの為の巣箱をMさんの家の庭にかけました。残念ながら昨年はブッポウソウはこの巣箱に入ってくれませんでした。巣箱は掛けたままにしておきました。
最近、Mさんにお会いしたら。ブッポウソウの巣箱にムササビが入ったようだ、と左の写真もいただきました。
ブッポウソウの巣箱かけの本には巣箱かけは4月になってから掛けるようにと、書いてありました。3月以前に巣箱をかけると巣箱をムササビに占領される可能性があるからです。(2018、4、15)

ネズミの頭(ネズミ目、ネズミ科)
10月の中旬に清流ランドの付近で見かけました。
ネズミの頭がきれいに切られて落ちていました。付近に肉の部分、足などが綺麗になくなっていて、内蔵だけが落ちており、その内臓にヨツモンシデムシが2頭来ていました。
キツネやテンのような大型哺乳類はネズミを襲った時には丸のみにしてしまいます。これは多分イタチの仕業でしょう。(2017、11、15)
 
キツネの足跡 アナグマの足跡
1月24日大雪が降り、25日朝、散歩に出かけました。キツネの足跡を見つけました。キツネの足跡はほぼ1直線についているので直ぐ分ります。上の写真はキツネが行ったり、来たりした後で何匹も歩いたわけではありません。
散歩から帰って、我家の庭を見たら愛跡があり、「足跡図鑑」を調べたらアナグマであることが判りました。(2016、2、15)

ヒミズ:(モグラ科)
散歩の途中で交通事故に遭ったヒミズを見かけました。頭胴長約100mm、尾長35mm。外見上はほとんど体の損傷は見かけませんでしたが、後ろ足に血がついているくらいでした。
下のジネズミに似た長い鼻を持っていますが、前足が大きく一目でもモグラの仲間と判ります。(2015、11、15)
 ジネズミ:(モグラ目、トガリネズミ科) ジネズミ:(モグラ目、トガリネズミ科)
3月30日に台所の出入り口近くの犬走りに死んでいました。
体長110mm、尾長40mm、体重11gでした。
台所の出口から外の世界に行くのには障害物がないので、外から我家にやって来た可能性が高いようです。
(2015、4、15)

ノウサギ:ウサギ科
1月下旬に御池に行く途中に見かけました。国道223線沿いの祓川部落から少し上がった辺りの道の傍でカラスが騒いでいたので車を止めて見たら大きなノウサギが死んでいました。多分交通事故で死んだものと思われます。全長50㎝以上もあり、立派な大人の雄でした。
お尻の所にカラスがつついた穴が有ります。(2015.2.15)

キクガシラコウモリ:キクガシラコウモリ科
このコウモリは御池から小池に行く途中にある東屋の天井に10月頃ぶら下がっていたものです。
このコウモリは三股町在住で東京農大の元教授で農学博士の吉行瑞子先生に同定していただきました。先生はコウモリの研究を長いことされていて、写真を見ただけで直ぐにキクガシラコウモリと言われました。
下の方に口のような丸い所がありますが、それは鼻葉といって、コウモリ自ら出した音波を受信する機関だそうです。鼻葉の直ぐ上に小さい黒い点が2ケありますがこれが目だそうです。
このコウモリの腕には金属の輪がはめられています。これは鹿児島県の研究者が付けたもののようです。
(2014、12、15)
 
アナグマ: 我家の庭にアナグマが掘った穴
近年、我家の周りでよくアナグマを見るようになりました。我家にも糞や足跡が確認されます。今年3月末に右の写真のように直径30㎝、深さ28センチほどの穴が掘られていました。
毎年恒例の町内の「花見会」で食事の後でご近所の方々と話していたら、納屋に死にそうなアナグマがいた写真を見せて頂きました。今度、アナグマを捕まえたら、私に連絡を欲しいとお願いしておきましたら。次の日に日渡さんから罠でアナグマを捕まえたとの連絡がありました。日渡さんの話では、牛の餌を食べてしまう害獣ではあるが、捕まえてみると可哀想で、自分では殺せないので役場と相談してみるとのことでした。(2014、4、15)
 
ジネズミ:モグラ目、トガリネズミ科
12月24日の寒い朝、我家の駐車場に死んでいました。駐車場は三方をブロックで囲まれていて、そこから脱出できず、凍死したものでしょう。家の前にある150坪ほどの放棄畑からきたのでしょうが、こんな所にジネズミが棲んでいるとは驚きです。
頭胴長は約70mm、尾長約55mmでした。初めてみる動物ですが、鼻が長く変な顔だなと思いました。(2014.1.15)

カヤネズミの巣:
温谷を歩いていたら道の放棄田の雑草の間に鳥の巣のようなものを見つけました。カヤネズミの巣です。
カヤネズミは日本で最も小さいネズミです。10円玉2枚分の重さしかありません。すなわち10gです。
野生動物観察のガイドブックにもネズミを見ることは困難と書いてあります。巣を見るだけで大満足です。(2013.9.15)

ノウサギの子供:
5月の連休明けに後川内の里山に行ってきました。水路の横の道を歩いていたら、下の水路で突然バシャ、バシャと魚の跳ねるような音がしたので水路覗いたら、このノウサギが水路を走って行くところでした。水路は深さ2m程もある3面張りで、人間でも出ることは困難な深さがありました。ノウサギは、体長は15センチほどしかないまだ子供でかわいいのですが、救う方法はありませんでした。(2013.5.15)
タヌキ?
5月の20日頃に庭の南西の隅に時々動物の糞がありました。そのうちに少し穴をほり、そこに貯め糞がされるに至って犯人はタヌキと「断定」しました。
足跡も土をならして写真に撮ってみました。
私の家は野中の一軒家ではありません。タヌキの住んでいそうな場所は我家から西の方にある森です。しかし、我家の西側に家が2軒あり、その向こうは道路を隔ててさらに家が3軒建っています。その向こうはさらに畑です。直線距離にして約150mほどもあります。(2012.6.15)
 
5月30日のタヌキの貯め糞 タヌキの足跡。10円玉くらい。子供のものか?

タヌキの糞?:
御池の散歩道の真ん中に動物の糞があり、ハエがたかっていました。勿論、シカやノウサギの糞ではありません。キツネやアナグマとも違います。イノシシの糞は見たことがありませんが、豚に似ているでしょうからこれも違うでしょう。消去法で考えるとタヌキになってしまいます。しかし、タヌキはタヌキの貯め糞と言って、こんなところにするとは思えません。しかし、タヌキの親子がここで次のような会話をしたのではないでしょうか
「おかあちゃん、ウンチがしたい」「お家のトイレまで我慢できないの?」「我慢できないよう」「しょうがないねぇ、じゃここでしなさい。」ということではないでしょうか?
(2012.5.15)

アナグマ:
4月の上旬、口蹄疫が発生する前、桜見物がてらに久しぶりに近くの牧場に散歩に行きましたら、アナグマに遭遇しました。奥のほうの牛の横を通り過ぎ、道の手前の柵の所まで歩いてきて、クローバーのなかに首を突っ込んで何か食べていました。私との距離は3メートルほどでした。
写真を撮っていたらそれでも気配を感じたのか、顔を上げ、目と目が合ってしまい、逃げ出すところの写真です。
逃げる時も脱兎の如くではなく、来た時と同じような歩調でトコトコと後の雑木林に消えて行きました。(2010.7.15)

鹿に食われたタケの葉:
2月の末に御池に行ったら、この光景に出会いました。鹿の首が届くところのタケの葉が無残に食われてありません。寒々しいと感じたのは私だけでしょうか。2004年に高原町に引っ越してきて以来、この御池で初めて見る光景です。鹿が増えすぎてついにタケの葉までも食うようになったようです。早く鹿を駆除しないと御池周辺の自然に悪い影響があるでしょう。(2010.3.15)
 
アナグマの巣穴と糞:
ある牧場の中の切通しの道の1.5Mほどの高さの土手にアナグマの巣を見つけました。そこは牧場を行き来するトラクターや小型トラックや人が一日に何度も通ります。そんな所に巣穴を掘るとは少々ビックリです。
入口には「これは俺の家だ」と表札代わりに糞がしてありました。アナグマの糞はこの写真のようにテカテカしているのが特徴であるとは野生動物図鑑に記載されています。(2009.9.15)

シカ:
シカには結構遭遇します。特に夜など思わぬところで会うこともあります。近年、この辺りでもシカが増えすぎてシカの害が問題になってきております。シカ駆除のためにいろいろ行われているようですが、増える一方で最近は遭遇する機会が多いように思います。しかしながら、写真に撮るのはなかなか難しいです。歩いていて遭遇すればカメラを構える前に逃げられてしまいます。これは車の中から崖の上で草を食べて居る所を写真に撮ったものです。車の中からだとシカも安心するのか逃げないようです。(2009.6.15)

アナグマ:
6月下旬の午後1時頃、皇子原温泉の近くで交通事故に遭ったアナグマを見つけました。生憎カメラを持っていませんでしたので道の端に死体を移してカメラを自宅に取りに行っている間に雨になってしまいました。未だ死後硬直していない死体でした。
こちらに来た頃はアナグマとタヌキの見分けがつきませんでしたが、すぐに簡単に見分けがつくようになりました。まず、この尻尾です。タヌキと比べると極めて貧弱なしっぽです。それから顔の形と鼻筋の白い線です。
夜向性なのに昼間よく見かけます。10メートル位の近さで遭遇したこともあります。アナグマは目が悪いという説も有るくらいです。(2008.7.15)
 
イノシシ:
1月27日に御池野鳥の森(御池キャンプ場)で例年通り野鳥観察会がありました。日本野鳥の会宮崎県支部の報告では今年のカモ類などの水鳥は945匹と昨年よりも更に少なくなっています。
さて、この日、高原町観光協会の準備した豚汁を頂き、昼食を取ったあとに、このキャンプ場にイノシシが現れ、一時大騒ぎになりました。参加者も野生のイノシシを見たことのある人は稀であり、特に子供たちが大騒ぎでしたが、皆で遠くから静かに見守りました。
尚、後日このキャンプ場の管理人に聞いた所ではイノシシの子供だったそうです。母親と子供が3頭いたそうですが、子供たちはどういうわけか皆死んだそうです。(2008.2.15)

猪のヌタ場:
10月の末に矢岳にミカエリソウを見に行った時に登山路の直ぐ側にありました。今年の春にはこのヌタ場は小さな水溜りになっており、カエルの卵が産み付けられていました。
春にはカエルが、秋にはイノシシが使う貴重な場所です。(2007.12.15)

タヌキ:
交通事故にあったタヌキの死骸です。比較的外傷が少なく綺麗な死骸でした。車ではねた人が死骸を道路の隅に移動させてありました。朝早く待ち合わせの場所に行く途中でしたので充分時間をかけて観察できなかったのが残念でした。
この1ヶ月の間に2回朝早く出かけることが有りました。2回ともにタヌキの死骸を見ました。(2007.11.15)

キツネ?の足跡:
我家の東側にあるイモ畑。トラクターで耕されてフカフカになった畑に一直線な動物の足跡。犬とキツネの違いはこの一直線にある、とモノの本に書いてあったように思います。
キツネの住む森は我家から真西に 100m 位離れています。しかし、その森からこの畑までは我家を含めて数軒の家の北側を迂回してこなければなりません。(2007.9.15)

ハツカネズミ:5月の下旬、朝の散歩の途中に道路の端に死んでいました。交通事故のようです。腸が一部出ていました。一応、袋に入れて自宅に持ち帰り、同定しました。ネズミの同定はけっこう厄介です。似たものにカヤネズミやヒメネズミなどがありますが、頭胴長、尾の長さ、毛の色などからハツカネズミであろうと断定しました。(2007.6.15)

ノウサギの糞:
ノウサギの糞をよく見かけます。この写真は田んぼの中に捨てられていた稲藁の屑の上にありました。ノウサギの糞は大抵木の生えていない開けてた場所にあります。ノウサギは開けた場所が好きなのでしょうか。
昼間このような開けた場所に出てくれば鷹などに狙われてしまいますが、ノウサギは夜行性なので大丈夫なのでしょう。(2007.1.15)

キツネ:
ついにキツネの写真撮影ができました。7月30日の夕間暮れ。時間は19:00時頃。日課の散歩の途中です。牛の放牧場の中。牛の冊のため、キツネがこちらに気付いていません。
2004年の6月末から9月初旬までに9回もキツネに遭遇しました。野生のキツネを見たことがなかったので大いに感動興奮しました。2005年は4回遭遇。今年はこれが最初です。この辺りもキツネにとってだんだん住みにくくなってきているのでしょうか。

キツネ:
8月4日やはり19:00ころ今年3回目の遭遇。牧場内で立ち止まってこちらをじっと見ています。(2006.8.15)

ヒミズ:
モグラ目モグラ科に属し、尖った長い鼻が特徴的な森に住むモグラのようです。半地下性の生活をしており、地表にもよく出現するらしいのですが、生きたものは見たことがありませんでした。
出口地区の迫を歩いていたら地面にハエが一杯たかっていました。ハエを追い払ったらヒズミが出てきました。左手を鳥かなにかに取られてしまったらしく手が片方ありませんでした。今朝の死骸という感じでした。
(2006.4.15)

リスのエビフライ?:
1月29日に御池で開かれた野鳥観察会に参加したときに御池のキャンプ村の松の木の下に落ちていました。誰が見てもリスの食痕、エビフライです。しかし、野鳥観察会に参加してみえた宮崎野生動物研究会の会長にお聞きしても宮崎県には野生のリスはいない、とのことでした。帰宅後本で調べても九州はほぼ絶滅とのことでした。考えられるのは飼われていたリスが逃げ出したものの食痕でしょうか?。(2006.2.15)

ノウサギの足跡:
2005年12月22日朝前夜から降った雪にくっきりとノウサギの足跡がありました。このように時々立ち止まってジグザグ行くのがノウサギの特徴のようです。足跡を追って行くとけっこう遠い距離を移動しています。その他の動物の足跡も探しましたが見つかりませんでした。05年の2月2日の降雪の時にはアナグマやキツネではないかと思われる足跡があったのに今回はこのノウサギだけでした。

コウベモグラ:
12月初旬、霜の降りた朝の散歩道で田の畦から出た所に死んでいました。モグラ塚はよく見かけますが、モグラの姿を見ることはめったにありません。頭胴長135cm、尾長20mmでした。九州南部のモグラは本州のものより小さいのが特徴だそうで、そう言われれば愛知県で見たものより小さいかなと感じました。
 
シカの足跡 シカよけの防護冊
シカの足跡はこの写真のように前足と後足が重なるのが特徴ですが、全ての足跡がこのように重なっているわけではありません。
近年、シカが異常に増え、人家の近くまで出てきて農作物を荒らしますのでこのような防護冊をめぐらす農家もいます。この足跡を撮影した場所は県道から5mくらいしか離れていない所で、しかも写真正面の山からこの撮影場所の空地に来るには人家と人家の間が50mくらいしか離れていない空地を通って来ています。
 
キツネの糞 糞の中身
またまたキツネの糞です。糞の左横の白いものはタバコのフィルターです。誤って食べてしまったようです。そのせいか糞の色も白っぽく不健康な感じです。中身は相変わらず毛の多いには驚かされますが、今回は骨が前回より少ないようです。子ねずみを沢山食べたせいではと、推測しています。
 
キツネの糞 キツネの糞の中身
いつもの散歩道でキツネの落し物を拾いました。この写真の他にも2個、計4個を道の端のアスファルト上に見つけました。4個を空き缶に水と共に入れ、5日後によく洗い茶漉しで濾過し乾燥したものが右の写真です。驚く程の動物の毛です。元の糞の倍位の容量がありました。あとは動物の骨。そして爪と思われるもの2本、鳥の羽の芯が3本でした。推測ですが、ノネズミを食べた糞と思います。
 
ノウサギの子供:
3月7日、午後、散歩の途中で道路わきの側溝の暗渠部からノウサギの子供が飛び出してきました。両手に乗るくらいの小さなノウサギです。近くの土手に隠れたつもりでジッとしているのを土手の上の道路から撮ったのが右の写真です。
更にもう少し近づいて撮ろうとしたら一目散に近くの雑木林に逃げ込みました。左の写真が走り出す直前のものです。
この子ウサギ無事にお母さんの所に帰ることが出来たかとても心配です。何故ならこの辺りは夕方になるとキツネが徘徊するからです。

ノウサギの足跡:
2月2日早朝の写真です。2月1日に雪が降り、そのあとウサギがやってきて足跡をつけ、その後また少し雪が降ったようで余り明確ではありませんがウサギの足跡のようです。

タヌキ?アナグマ?:
やはり2月2日の写真です。動物が歩いた後に雪が降ったのと、手元の参考資料が充分ではないのでタヌキなのか、アナグマなのかはっきりしませんが、そのどちらかであろうと思われます。

鹿の糞:
我が家より山に近いところに住む人の話ではシカにはよく会う。特に薄暮の頃には珍しいことではない、とのことでした。よく出るところを教えていただいて、夕暮れ前から、2日間、静かに待ちましたが、会うことは出来ませんでした。
この写真は御池のキャンプ場の前の芝生に今朝の糞、という感じで落ちていたものです。秋になってキャンプ場に人がいなくなりシカが遊びに来るようです。

テンの糞:
六月ころ、クマイチゴをたくさん食べらしく糞の色はピンク色、クマイチゴの種子が一杯です。いわゆるテンの見せ糞でアスファルト上にありまして。

イノシシの足跡:
イノシシのヌタ場にあったイノシシの足跡です。
写真がよくないので見にくいのですが、写真をじっとみていると何となく判るかと思います。
イノシシの親子連れに2回会いました。勿論、人間を見れば一目散に逃げますのでその写真を撮ることは極めて困難です。
| № |
種名 |
目 |
科名 |
| 1 |
ニホンノウサギ |
うさぎ目 |
うさぎ科 |
| 2 |
ニホンジカ |
偶蹄目 |
しか科 |
| 3 |
イノシシ |
偶蹄目 |
いのしし科 |
| 4 |
アナグマ |
食肉目 |
いたち科 |
| 5 |
イタチ |
食肉目 |
いたち科 |
| 6 |
ニホンテン |
食肉目 |
いたち科 |
| 7 |
キツネ |
食肉目 |
いぬ科 |
| 8 |
タヌキ |
食肉目 |
いぬ科 |
| 9 |
コウベモグラ |
もぐら目 |
もぐら科 |
| 10 |
ヒミズ |
もぐら目 |
もぐら科 |
| 11 |
ハツカネズミ |
げっし目 |
ねずみ科 |
| 12 |
カヤネズミ |
げっし目 |
ねずみ科 |
初回:7種類
その他アライグマを見たという話も聞きましたが私自身が見ていませんのでここに記載しませんでした。
|






 (ネコ目イタチ科)
(ネコ目イタチ科)








 ジネズミ:(モグラ目、トガリネズミ科)
ジネズミ:(モグラ目、トガリネズミ科)



































